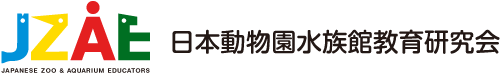第 63回日本動物園水族館教育研究会 札幌大会 開催報告
開催日時:2023 年 1月 20 日(金)~ 1 月 21 日(土)
開催地:札幌市円山動物園
共 催:札幌市円山動物園
大会テーマ:「動物福祉と教育」
第61回、第62回のWeb大会を経て、今回ははじめてのハイブリッド開催となりました。
会場では席と席の間を広くとり、参加者は40名までとしました。
オンライン参加、会場参加からお一人ずつ、参加報告をご執筆いただきましたので、以下にご紹介いたします。
今回の開催にあたっては、札幌市円山動物園のみなさまに、ご準備、大会中のさまざまなサポートをいただきましたこと、深く御礼申し上げます。
第63回日本動物園水族館教育研究会 参加報告(オンライン参加)
下関市立 しものせき水族館「海響館」
井上美紀
今回はオンサイトとオンラインのハイブリッド形式で開催され、雪化粧の動物園をいつか見てみたいと思いながら、私はオンラインで参加しました。今回で5回目の参加となりましたが、本研究会に参加をするたび、より良い学びに繋げるための工夫や、学びを評価する方法について知る機会になり、刺激を受けます。水族館と動物園の教育普及の題材は多岐にわたり、各園館の特徴を生かした取り組みにいつも心揺さぶられます。
本大会で印象に残っている発表は、学校教育現場で実践された事例です。水族館動物園の来館者、来園者向けに実践する場合とは異なり、学校では必ずしも皆が生き物に興味関心をもって授業に臨んでいる子どもたちばかりではない中で、授業で動物福祉を題材にすることはハードルが高いのではいないかと思い込んでいましたが、発表を拝聴し、学校の授業でも工夫することで取り入れることができるのだと感じました。実践中は、双方向の会話、とにかく褒める、間違いを否定せずに一緒に答えを考える、なぜそう思ったのかを汲み取ることを意識しながら進めたとのことでした。授業は飼育員から生き物の魅力(特徴)を学んだあとに、個々で動物の気持ちや、動物のためにできることを考え、さらにはクラスみんなで一緒に考えようという流れでした。生き物を知ろうと思う気持ちから、生き物の気持ちを考える、このステップが子どもたちなりに動物福祉を考え、生き物に心を寄せることに繋がっていく素敵なプログラムだと感じました。
これまでも学校からキャリア教育向けに水族館での仕事内容や、仕事に就くためにどんなことを学んだのかなどを中心に話をする機会がありましたが、生き物と関わる仕事だからこそ「命と向き合う」仕事について知ってもらい、「命の向き合い方」について関心や興味を持ち、もっと生き物を好きになってもらえるような学習プログラム作りができればと思い描いています。
ハイブリッド式での研究会の開催は現地とオンラインを繋ぐ大変さがあったと思います。この場をお借りして、関係者の皆様に感謝申し上げます。
第63回日本動物園水族館教育研究会 参加報告(会場参加)
豊橋総合動植物公園
動物研究員
櫻庭陽子
雪が降りしきる厳冬期の札幌市円山動物園において、第63回動物園水族館教育研究会が開催されました。今回は「動物福祉と教育」というテーマのもと、オンサイト(定員40名)とオンライン(定員180名)でのハイブリッド形式で行われました。私自身は昨年初めて参加し、今回で2回目でしたが、研究会自体は3年ぶりの対面ありの開催でした。オンサイトでは約40名、オンラインでは常時100名近くが参加していました。

集合写真
発表は「動物福祉と教育」というテーマから、動物に負担なく教育プログラムを組む事例や、オンラインで動物福祉に関する教育プログラムを実施する等、各園館で試行錯誤した取り組みが多く発表されていました。昨今のコロナによる感染症対策の一環として行われるようになったオンラインの教育プログラム紹介も多かったですが、オンラインに向く・向かないプログラムがあるようにも感じました。コロナが収束してもオンラインの活用は継続されると思いますので、オンラインに向く・向かない教育プログラムをまとめる調査も必要だと感じました。
2日目の午後は円山動物園スタッフのガイド付き見学会でした。私自身は飛行機の関係でホッキョクグマ館しか見学できませんでしたが、やはり解説付きだと非常に勉強になりました。ホッキョクグマ館は2018年3月にオープンした施設で、AZAやカナダのホッキョクグマ施設基準に沿った施設になっているそうです。バックヤードには行けませんでしたが、防音がしっかりした産室があるとのことで、北海道の自然環境を活かした繁殖に期待がかかります。ほかにも、施設内にはモニュメントや地球温暖化に関する啓発用の掲示物がたくさんあり、教育にも力を入れている様子が分かりました。ホッキョクグマも寒くて雪深い北海道だからか、非常に生き生きと動きまわっていました。

広い屋外放飼場(ホッキョクグマ)

壁一面の展示物(ホッキョクグマ)
研究会の合間やお昼休み時間には円山動物園内をまわり、冬が厳しい北海道ならではの充実した屋内施設に圧倒されました。特に見学会では行けなかったアジアゾウ舎は、広いだけでなく、床には砂を敷き、環境エンリッチメントを充実させ、トレーニングの時間も十分とっているとのことでした。来園者側にも広いスペースを設けており、ゾウが水に入っている様子やトレーニングを見ることができるエリアもありました。掲示物やモニュメント、デジタル技術を用いたクイズ等も充実していました。

広い屋内放飼場(アジアゾウ)

来園者エリア

トレーニングが見学できる(アジアゾウ)
個人的に興味をひいた施設は爬虫類・両生類館です。1階中央にガラス張りの「センターラボ」という研究スペースがあり、繁殖などを行っているようです。その様子も来園者が見ることができます。また、北海道の気候をうまく利用して、雪の中で野生の様子を想像できる施設もすてきでした。オオカミの放飼場は、針葉樹が植わり、森の中からオオカミが現れるような姿を見ることができました。エゾユキウサギも、白い冬毛で雪に隠れている姿を見ることができ、擬態を実感できました。また面白い(怖い?)と感じた展示物が、「さっぽろヒグママップ」というもので、そこには令和4年度のヒグマ出没情報が示されていました。札幌市中心部の地図があり、そこに赤い点でヒグマが出没した箇所が示されていました。住宅街近くまでヒグマが出てきていることが良くわかり、これも北海道ならではと思いつつも、少し恐怖も感じました。

オオカミの屋外放飼場

擬態するエゾユキウサギ

ヒグマ出没情報マップ
今回の研究会では、オンサイトの強みを生かし、発表だけでなく、人脈作りから施設見学まで充実した時間を過ごす事ができました。オンラインでは移動時間も旅費もいらず気軽に参加できるメリットもあるため、その人の希望によって選択できるのは良いことだと感じました。一方で、運営側の準備は大変だろうと容易に想像ができ、施設や人手、ネット環境等が大きく影響しないようサポートが必要だと感じました。いずれにしても、コロナの影響で研究会や教育プログラムの手法に多様性が生まれるのも、一つ良かったところでもあるかなと前向きにとらえ、今後も勉強していきたいと思います。